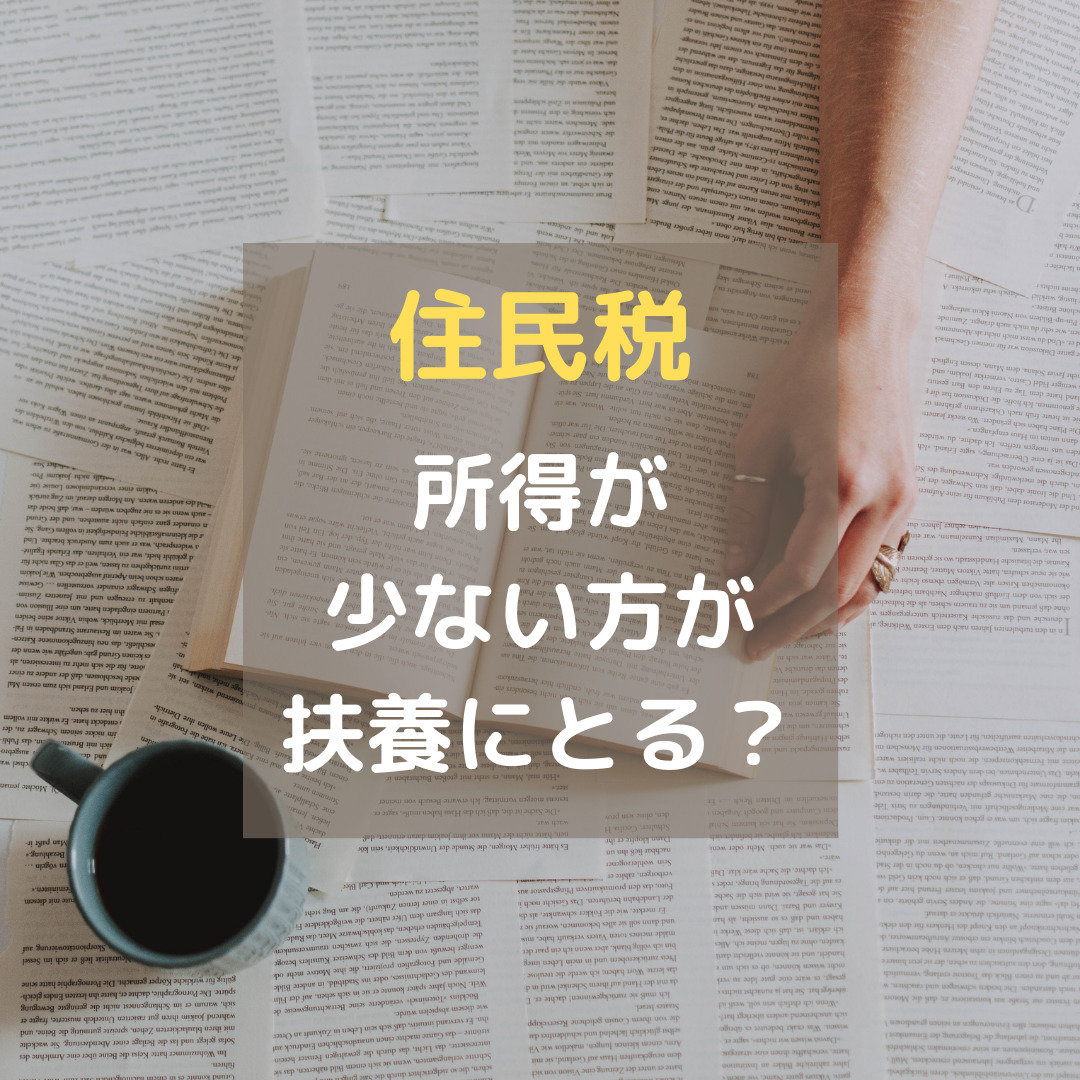扶養と言ったら、所得が多い人が少ない人や収入ゼロの人を扶養にするってことでしょ?
このように感じている人は多いのではないでしょうか。
扶養のイメージは確かにそうですよね。
俺がパートの妻と子供を扶養しているんだ!という旦那さんも多いと思います。
ですが、実は所得が少ない方が小さい子どもを扶養に取ったほうがいい場合がある!というのをご存じですか?
「所得が少ないのに扶養に取るとはどういうこと?」と思われるかもしれませんが、ある計算に当てはまる場合は、住民税という税金の金額が大きく変わることになるのです。
今日は、所得税の陰に隠れるけれども結構重要な住民税についてお話していきたいと思います。
ブログランキング参加しています。
ぽちっと応援よろしくお願いします。

ファイナンシャルプランニングランキング
所得税も住民税も16歳未満の子どもは扶養控除額が0円

年末調整や確定申告などの際に、扶養控除について記入する欄があります。
子どもや両親など、生計が一緒で収入のない(少ない)人を扶養控除として申告することができます。
これは人的控除(じんてきこうじょ)と言って、申告するだけで控除額が増えて節税につながる簡単な控除の一つです。
例えば、配偶者控除は所得から38万円控除することができます。
所得が200万円だったときに、200万円そのままに税金がかかるよりも38万円を引いた162万円に税金がかかる方が安く済みますよね。
ですが、この扶養控除は小さいお子さんは対象外になっているのをご存じですか?
平成23年分の所得税より、それまで該当となっていた16歳未満の子どもの扶養控除が廃止されました。
現在は16歳未満の子どもを扶養として申告しても、控除される金額は0円です。
それより前は、所得税だと38万円子どもの扶養で控除されていたので、金額のインパクトが大きいですよね。
余談ですが、これは児童手当の改正に伴って行われました。
実際に窓口では混乱が起き、高所得で児童手当が減額になっている方々からの質問がとても多かったです。
「児童手当ももらえないのに控除もないの!?」
たしかに、税が上がるだけでは何のメリットもありませんもんね…。
さて、現在では所得税には関係ない「16歳未満の子ども」ですが、確定申告の申告書や年末調整の書類ではどうやって書けばいいのでしょうか。
書類の中では「住民税に関する事項」という欄が設定されています。
源泉徴収票では扶養の申告書の下の欄、確定申告の書類では二表と呼ばれるページの左下です。
その欄に記入することで、扶養に取っていることを示します。
「税金の控除にならないのに、なんでわざわざ書くの?」と思われた方、するどいです。
この「16歳未満の扶養親族」は、所得税では全く関係がありませんが「住民税」で非常に重要となってくるのです。
【非課税になるかも】住民税は16歳未満の子どもの数がカギ
先ほど、「住民税に関する事項」という欄に記入すると解説した通り、住民税の計算を行う際には16歳未満の子どもを含めた扶養の人数がとても重要になってきます。
住民税の基本的な計算方法は、控除の金額は異なりますが所得税と同様です。
1月から12月までの1年間で得られた収入から所得を計算し、控除を引き算し、最終的な税金の額を計算します。
ですが、住民税には所得税とは大きく異なる点が2か所あります。
- 均等割と所得割の2種類の合計で住民税が決定する
- 所得があっても非課税になる場合がある
それぞれを見ていきましょう。
1.均等割と所得割の2種類の合計で住民税が決定する
所得税では、所得の金額から控除する金額を差し引いて、所得がまだ残る場合には所得税がかかります。
控除額の方が大きければ、所得税は0円になります。
住民税では、この所得に対しての税金を所得割(しょとくわり)と言います。
しかし、住民税では所得割に加えてもう一つ、均等割(きんとうわり)という計算があります。
均等割は、一定の所得があった場合には必ずかかるもので、所得額<控除額となった場合でもかかるものです。
つまり、所得が少なく控除が大きい場合は、所得税がかからなくても住民税だけはかかるという可能性があるのです。
あなたの周りで「103万円で扶養の範囲内で働いているのに、税金を払えって通知がきた!」という方はいませんか?
それも、この住民税が原因となっているパターンです。
均等割の金額は住んでいる地域によって金額が異なりますが、4,000円から6,000円のところが多いのではないかと思います。
2.所得があっても非課税になる場合がある
所得税では、所得よりも控除が少ない場合は、基本的には税金がかかります。
※災害減免法に基づく減免など、一部税がかからない場合もあります。
しかし、住民税の場合は所得よりも控除が少ない場合でも、非課税(0円)となる場合があります。
寡婦、ひとり親、障害があると申告している場合は、所得が135万円まで非課税です。
未成年者も所得が135万円までは非課税です。
収入に直すと204万円程度までは住民税がかからないということになります。
また、それぞれの市区町村で条例によって非課税になる所得を決めています。
例えば渋谷区では、以下の計算に当てはまる場合は住民税が非課税になります。
合計所得金額≦35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円
(参照 渋谷区公式サイト)
※令和2年度の計算であるため、令和3年度(令和2年分)の計算額は変更になる可能性があります。
文字ばかりの計算式だと難しいので例を考えてみましょう。
例えば、妻と大学生の子ども1人を扶養としている場合には、以下のようになります。
合計所得金額≦35万円×3人(本人と扶養が2人)+21万円=126万円
所得が126万円以下、収入に直すと191万円程度までは非課税になるということです。
この計算の際は、所得税で見向きもされなかった16歳未満の扶養者の人数も含めることになります。
年収191万円程度では食べていけないよ!という声も聞こえてきそうですが、確かに稼ぎ頭の世帯主さんではそうかもしれません。
ですが、パートや時短勤務などで収入が多くない配偶者の方の場合ではどうでしょうか。
仮に3歳と5歳のお子さんがいらっしゃる場合、そのお子さんを年末調整で配偶者の方が扶養に取れば、191万円程度までは住民税がかからないということになります。
通常191万円収入がある場合、基礎控除だけですと9万円強住民税がかかります。
これが0円になるというのは非常に大きいでしょう。
行ったことは、16歳未満の子どもを所得が少ないほうの方の扶養として申告しただけです。
その場合は、年末調整で元々入っていた扶養を抜くと手当などが変わってしまう場合があります。
本来社会保険の扶養と税法上の扶養は異なるものですので別々でも構わないのですが、念のため確認したほうが良いかもしれません。
住民税を全額0にはできなくても安くなる場合がある
また、均等割はかかるけれど所得割がかからないという場合もあります。
再度、渋谷区を例にとりますと計算式は以下のとおりです。
前年中の総所得金額など≦35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円
(参照 渋谷区公式サイト)
※令和2年度の計算であるため、令和3年度(令和2年分)の計算額は変更になる可能性があります。
均等割が非課税となる式の、21万円の部分が32万円に変わっています。
先ほどの本人と扶養が2人の場合であれば、所得137万円、給与収入に直すと207万円程度までは所得割がかからなくなります。
住民税が全額0円になるわけではありませんが、6,000円ほどまで住民税が下げられれば、その分貯蓄や投資に回すことができますね。
繰り返しますが、ただ所得が低いほうの方が16歳未満の子どもを年末調整で扶養申告するだけです。
お住まいの市区町村によって非課税となる金額は変わります。
HPで確認していただくと、該当になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まとめ
今回は、住民税が扶養の人数によって非課税となる場合について解説しました。
所得税でも住民税でも、16歳未満の子どもを扶養にとっても扶養控除の額は0円です。
しかし、住民税が非課税になる所得の金額を計算する場合には、扶養に取っている16歳未満の子どもの数も計算対象となります。
そのため、夫婦の中で所得が少ない方の扶養とすることで、夫婦全体の所得税の金額は変えずに住民税の金額を下げることができる場合があります。
誰でも使えるわけではありませんが、お住まいの市区町村の非課税対象金額をチェックしてみるのも良いかもしれません。
脱税はだめですが、使える節税はどんどん使い我が家の資産を守っていきましょう。